サービス
- HOME
- サービス
- 地方独立行政法人労働者健康安全機構 浜松ろうさい病院(静岡県浜松市)
地方独立行政法人労働者健康安全機構 浜松ろうさい病院(静岡県浜松市)
事例 - 地方独立行政法人労働者健康安全機構 浜松ろうさい病院(静岡県浜松市)
病院機能評価受審を医療安全体制強化に活用
~受審のプロセスを通じて院内コミュニケーションが活発に~
浜松ろうさい病院は、2024年5月に病院機能評価を更新受審。「一般病院2」で認定を受けました。
本稿では、病院機能評価受審の目的や成果について、院長の江川裕人先生、看護部長の三ツ星恵子様、事務局長の長尾久幹様、前事務局長(現・富山ろうさい病院事務局長)の佐藤久仁雄様(Zoomでのご参加)、総務課長の世一泰弘様にお話しを伺いました。
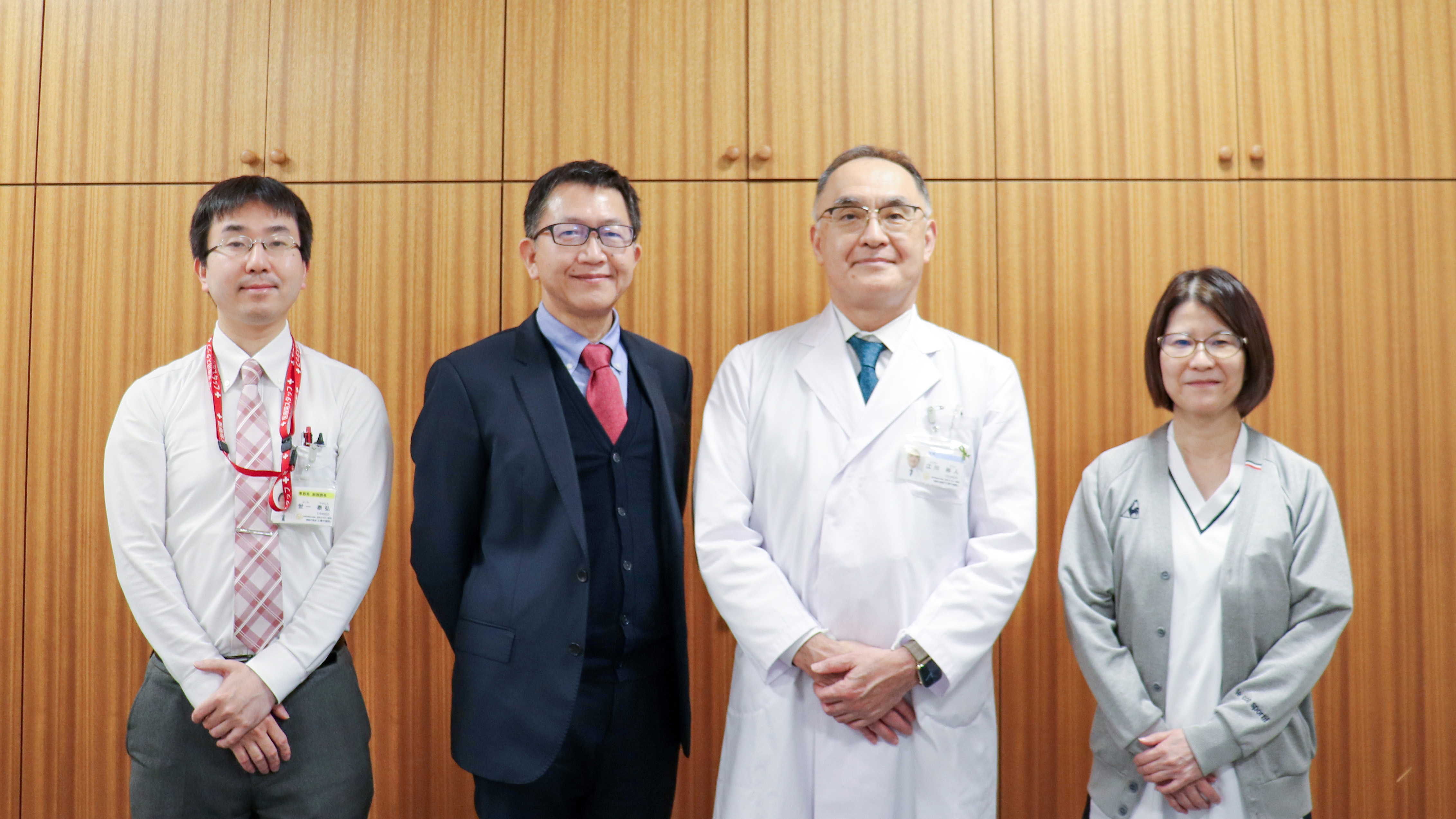
- 法人概要
-
- 名 称:
- 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松ろうさい病院
- 住 所:
- 静岡県浜松市中央区将監町25
- 院長:
- 江川裕人
- 病床数:
- 312床
- 診療科目:
-
内科、精神神経科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、 整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、 婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、健康診断部

病院外観
病院機能評価認定取得の意義を教えてください。
江川院長:
当院は地域の全ての皆様の全ての疾患に対し高度な専門医療を提供する地域の中核病院として、この10年で消化器や呼吸器、整形外科だけでなく、心臓や大血管などの循環器領域および脳血管領域の診療科と麻酔科の質的・量的増員で高度医療を充実させています。救急医療では、市内の二次救急輪番制に参加して、職員一丸となって対応することで病床あたりの救急搬送件数は市内7病院で一番多くなっています。
私は2023年4月に当院に院長として着任しました。以前から医療安全が病院運営にとって一番重要であると考えており、そのためには病院も一つの企業体としてガバナンスを利かせる必要があります。病院機能評価の受審を通して、例えば同意書や手順書を院内で規格を統一していく機会になります。
受審に取り組む意義として、院内のコミュニケーションが活発化することがあります。医療安全を推進するためには院内のコミュニケーションが重要です。コロナ禍の間にコミュニケーションがとりにくくなっていました。一定期間で集中的に、病院機能評価の認証を受けるという一つの目標に向かって、部門横断的に取り組む良い機会になりました。
また、受審に向けた準備の中で、それぞれの部署が行っている業務や院内の優秀な人材が可視化され、よく見えるようになりました。当院の良い財産をあらためて理解する機会にもなりました。

三ツ星看護部長:
師長などの現場のリーダー職員が、各部署で看護の実践をまとめていく過程において、皆で一緒に取り組むことで課題が見えてきたことが良かったです。
具体的には、看護の要点はたくさんあるのですが、全症例について、褥瘡、医療安全、栄養の評価などの同じ視点で重要なポイントを振り返る機会になりました。

佐藤前事務局長:
日常業務でも解決すべき課題は色々とありますが、いざ解決したいという声が出てきても、忙しい医療現場では、途中で尻すぼみになってしまうことも往々にしてあります。病院機能評価受審というイベントを通して、受審期限があり逃げられないというプレッシャーも、一人ひとり共有できたと思っています。

受審に向けてどのような院内体制、準備体制を構築されましたか。
江川院長:
目的を繰り返し院内に伝えることを意識しました。一般的に、院長はキックオフと模擬審査の際などに2~3度話すだけのことが多いと聞いています。私は、職員の意識がぶれないよう、場面場面で目的を強調しました。
佐藤前事務局長:
病院機能評価は認定を取ることが目的になってはいけません。病院を良くしたいという思いがないと“認定証欲しさ”のように職員から透けて見えることは良くないと考えました。認定を取ることが目的ではないことをきちんと伝えていきました。
コンサルタント頼みになってしまわないよう、主役は私たちであるという意識に自分を追い込んでいきました。例えば、自己評価調査票を記載してもらう際には、課題も含めて包み隠さず記載するよう、現場に促しました。結果、「ここまで書くか」というレベルまで記載してきてくれました。これを経営幹部がきちんと受け止めて、現場の意見を吸い上げることができる体制にしました。
病院機能評価の評価項目に、経営層が引っ張っていく組織作りになっているかということが書かれています。各部署の責任者がまとめた資料を、私たち経営幹部がよく見ていない状態で提出してしまうと、いざ訪問審査を受けるときに指摘を受けることになってしまいます。現場の意見を吸い上げて、それを受け止めるということを意識しました。
江川院長:
課題に目を向けるとどうしてもお互いできていないところをけん制し合うような雰囲気になりがちですが、当院では「上も頑張っているから私たちも頑張らないと」という雰囲気ができていたと思います。
長尾事務局長:
私は審査日の直前に佐藤前局長と入れ替わりで着任したのですが、病院機能評価の受審準備に積極的に参加し、訪問審査では部署訪問に立ち合うなどして、職員と同じ意識を持つようにしました。

コンサルティングサービスを活用したメリットがあれば教えてください。
佐藤前事務局長:
当時、院長をはじめ、更新審査に関わる中心メンバーは人事異動で着任したばかりで、当院での前回の受審を経験していませんでした。時間的な制約もある中、私自身は相当プレッシャーを感じていました。もちろん、周囲には感じられないように努めましたが、最初のうちは、受審準備を始めると院内がどういう雰囲気になっていくのか想像がつかなかったです。そこで、効率的に進めるためには様々な病院の支援を経験している外部のコンサルタントの助力も必要だと考えました。
世一総務課長:
院内のメンバーのみだと、できていないことに目が向きがちになります。川原経営さんにコンサルティングしていただいて良かったことは、もちろん修正すべき点はご指摘いただく一方、できている点をアピールするようご助言をいただけた点です。おかげさまで自信を持つことができました。私も他院に在籍していた時は病院機能評価に携わることはなかったので初めてでしたけれど、非常に良い経験ができました。

三ツ星看護部長:
自己評価調査票の作成の仕方については、川原経営さんの助言が大変参考になりました。日本医療機能評価機構のサーベイヤーも驚いてらっしゃいました。これほどポイントを押さえて、“痒いところに手の届く”レポートはないとおっしゃっていただけて、完成度が高かったとご評価いただけました。
病院機能評価受審によって、どのような成果がありましたか。
江川院長:
冒頭にも述べましたが、医療安全などを念頭にして病院でさまざまな規格を統一することができました。同意書ひとつをとっても、意識が高い医師もいれは、優先順位が別にある医師もいます。そのままにしておくと色々なパターンができてしまいます。個別の患者さんに対応することは大事ですが、組織としては現在の医療水準において満たすべきレベルを担保する必要があります。
また、病院を良くしようという意識を全体の雰囲気として作ることができたと思います。病院機能評価受審直後の全体会で、私は職員に向けて全員が主役になることができたという話しをしました。また、人材育成です。世一総務課長が成長されました。ご本人はあまり気づいていないかもしれませんが、表に立ってプロジェクトを引っ張っていくことに対して、何もためらいなく、各部署をうまく動かしてくれるようになりました。
三ツ星看護部長:
看護部でも、師長が病棟で“わちゃわちゃ”議論しながら取り組み、業務改善していくためにいいムードを作ることができました。医師に対しても、ケアプロセスにどう参画してもらうかという“作戦会議”を行うなど、職員一人ひとりが主体性をもって取り組めました。
忙しい医師には病院機能評価の評価項目やコンサルタントからの情報提供で、求められているエビデンスを提示しながら、医師に働きかけ、巻き込むように意識していきました。
病院機能評価の受審の過程で洗い出された課題には、受審のプロセスで改善できるものとそうでないものがあります。自己評価調査票作成期間は、オンラインで週1回川原経営さんにも参加していただき内容を検討しました。それによって、各担当者が記載した項目に受審準備の中で解決されていない問題についても、院長、事務局長、私が中心となって、対応策を考えるきっかけになりました。
今後の展望をご教示ください。
世一総務課長:
病院機能評価受審がきっかけだったと言っても良いと思うのですが、臨床研修の第三者評価を受ける予定にしています。もちろん、目的はきちんとした臨床研修体制を構築するためですが、外部から審査を受けた経験や今回準備した資料は活用していきたいと思っています。
病院機能評価をこれから受審される医療機関の皆様へ一言お願いします。
江川院長:
繰り返しになりますが、受審の目的を大事にしてほしいです。当院であれば医療安全。そしてそのためのコミュニケーションの活性化でした。目的に向かって一丸となることが重要です。
三ツ星看護部長:
病院機能評価の受審は、多職種の協力が重要だと思っています。そのためには看護部が果たす役割は大きいです。現場の師長が目的意識をもって取り組まれるようにすると良いと思います。
長尾事務局長:
事務職は医療の中身に直接的には携われないかもしれませんが、現場のさまざまな取り組みの精度を上げるよう支援できます。事務局内での連携、例えば総務課と医事課といった具合に、事務局全体としての視点をもって取り組むことが大事かと思います。
貴重なお話をありがとうございました。
取材日 2025年2月14日

 お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ メールフォームからのお問合せ
メールフォームからのお問合せ