ブログ

医療福祉の未来地図
VOL.73「自己評価研修の有効性」
皆さん、こんにちは!
川原経営の神林でございます。
年末にかけて、仕事の整理に勤しんでいる方は多いのではないでしょうか。
弊社においてもテレワーク勤務の併用が継続しているため、
以前に比べると出社は少なくなりましたが、
デスク回りを整理して、新年に備えたいと考えています。
さて、新年を迎えると、年度末にかけて人事考課を実施する園は少なくないはずです。
人事考課については以前、
で詳しく書きましたのでご参考ください。
人事考課できちんとした評価を行うためには「考課者研修」が不可欠です。
評価基準を考課者が共有することで、
組織内での評価のズレ・ブレを最小限に留めることができます。
同様に、部下の自己評価と上司の評価のズレにも注意が必要です。
ズレがあまりに大きい場合、
補正の説明だけで大切な面談の時間が取られてしまう可能性があります。
上司と部下の間でも、ある程度、評価基準が共有できていれば、
それを前提とした評価の擦り合わせが行えます。
今回は、「自己評価研修」について、説明していきます。
1.研修の内容
自己評価研修では、
いきなり「評価のつけ方」の説明をするのではなく、
園の人事考課制度を理解してもらうことから始めます。
・人事考課の目的
・評価結果はどのように処遇に反映されるのか
・年間のスケジュール
などについて、まずは全体像をお伝えします。
特に、その年に新たに入職された方には、丁寧な説明が必要です。
2.自己評価のつけ方
自己評価のつけ方をレクチャーする際には、
・評価の対象となる行動
・評価の段階
について、事例を交えて説明することが効果的です。
例えば、
・自宅(時間外)で自己学習した行動は、評価の対象としてよいか
・地域(職場外)の交流イベントに参加した行動は、評価の対象としてよいか
「行動の選択」には一定のルールがある旨を理解してもらいます。
評価の段階については、
5段階・4段階・3段階など、園によって様々ですが、
基準となる評価を軸に、
「根拠(事実)に基づいた」段階の選択が必要となります。
(例:S・A・B・C・Dの5段階の場合、基準となる評価Bを軸に、根拠に基づいて選択。)
面談の際にきちんと自己評価の根拠を説明できるよう、
準備してもらうことも大切となります。
せっかく制度が整備されていても、
運用するためのルールが共有されていないと、
上司部下の関係性がギクシャクしてしまうリスクがあります。
この点に関してはできるだけ手間を惜しまず取り組まれると、
より良い人材育成につながるでしょう。
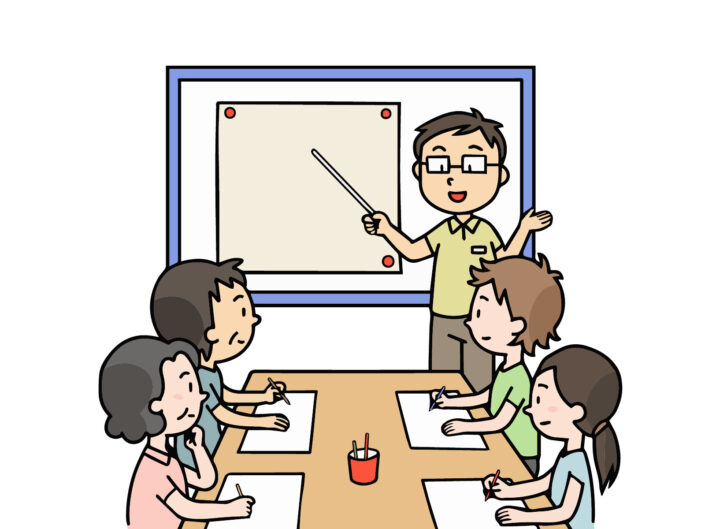

- ◆ 神林 佑介 プロフィール ◆
- 経営コンサルティング部門 副統括。保育園、老人ホームで働いた後、オーストラリアへ留学。施設での経験を活かしたいという想いをもって2012年に川原経営に入社。保育所・介護施設等を運営する社会福祉法人の給与・人事考課・研修の制度構築支援に従事。その他社会福祉法人の設立・合併・事業譲渡支援など、医療・福祉経営に関する幅広いコンサルティングを行っている。
保有資格:行政書士・保育士・社会福祉士
著書:「地域に選ばれる特別養護老人ホームの作り方」「介護ビジネスの動向とカラクリがよ~くわかる本」
CONTACTお問い合わせ
ご相談・資料請求など、
メールフォームよりお気軽にご連絡ください。
