サービス
- HOME
- サービス
- 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院(山梨県甲府市)
地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院(山梨県甲府市)
事例 - 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院(山梨県甲府市)
自院の強みと問題点の明確化に病院機能評価を活用
~円滑な院内コミュニケーションによる課題解決で医療の質向上を実現~
山梨県立中央病院は、2024年8月に病院機能評価を更新受審。「一般病院2」で認定を受けました。
本稿では、病院機能評価受審の目的や成果について、院長の小嶋裕一郎先生、副院長兼看護局長の石倉晴美様、事務局長の山本英治様、企画経理課長の丸山雅之様にお話しを伺いました。

- 法人概要
-
- 名 称:
- 独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院
- 住 所:
- 山梨県甲府市富士見1丁目1番1号
- 院長:
- 小嶋裕一郎
- 病床数:
- 644床
- 診療科目:
-
内科(呼吸器)、内科(消化器)、内科(循環器)、内科(糖尿病・内分泌)、内科(腎臓)、内科(血液)、内科(リウマチ・膠原病科)、女性専門外来、精神科、神経内科、小児科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、小児外科、形成外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、産科、新生児内科、眼科、麻酔科、放射線治療科、耳鼻咽喉科、歯科口腔外科、放射線診断科、病理診断科、救急科、緩和ケア科、化学療法科、リハビリテーション科、臨床検査科

病院外観
※本記事の掲載内容は取材時(2025年1月20日)現在の情報に基づいています。
病院機能評価認定取得に取り組まれた経緯を教えてください。
小嶋院長:
当院は救急医療、周産期医療、がん治療において、山梨県の中心的な役割を果たすほか、総合病院としての医療機能を備えています。学術面においても成果を残し、将来を担う若手医師を教育する臨床研修指定病院としても誇れる実績を有しています。
さまざまな取り組みを日々しっかり行っているつもりではありますが、病院機能評価の受審により、改めて客観的に病院の問題点を明らかにし、さらに病院運営を改善していくことができるという思いで、更新審査に臨みました。

S評価を得た項目について、日々のお取り組みをご教示ください。
小嶋院長:
2024年12月6日に更新認定を頂き、S評価を2項目取得できました。一つは感染制御について、もう一つは救急医療についてです。S評価を得られたこれらの項目は、普段実践していることが改めて評価されたのだと思い、自信にもなりました。日頃から感染対策は徹底していると自負しています。院内では、病棟にとどまらず、放射線部、内視鏡などの検査部、栄養管理科などを含めた定期的なラウンドを実施しています。ターゲットサーベイランスも幅広く定期的にデータを集計し、院内で議論しています。また、当院では県内外のさまざまな病院と半年に一度、相互評価を実施し、感染対策向上につなげています。新型コロナウイルス流行のピーク時には総合診療科の医師や感染管理認定看護師が他院、他施設に赴き指導していました。地域においてリーダーシップをとって感染対策を行っており、こういった日々の取り組みが評価されたと思っています。
石倉副院長:
職員一人ひとりが感染対策の取り組みを粛々と徹底することが大事です。そのために認定看護師の更なる育成を目指しています。感染管理認定看護師が根拠をもって各部署に感染対策の重要性を伝えてくれているため、院内職員全体の意識が高くなってきています。
その結果か、職員がインフルエンザや新型コロナウイルスなどにあまり感染しません。感染対策を徹底することにより、医療提供が滞りなく行われており、私はこういう点がS評価につながったと思っています。
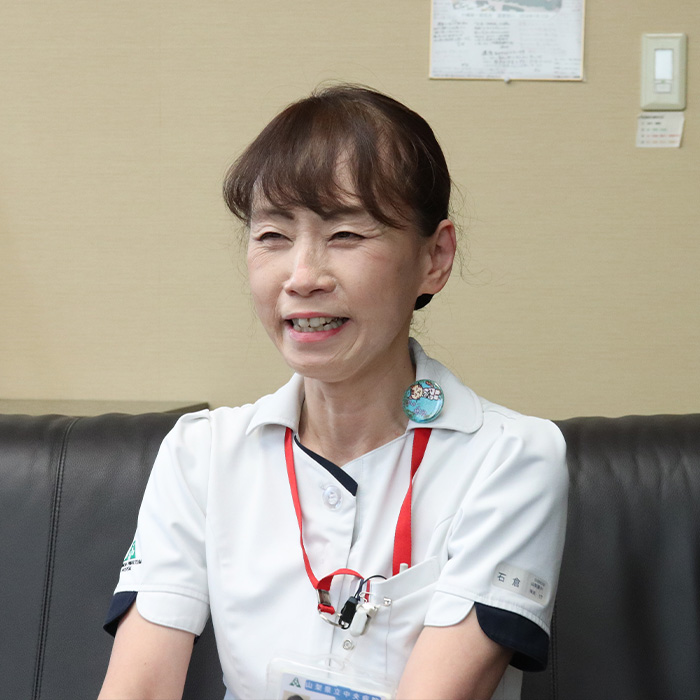
小嶋院長:
救急医療について、当院は山梨県民の生命を守る“最後の砦”と考えています。ドクターヘリも安定的に運用できており前月(2024年12月)の出動件数も30件程度ありました。救急車応需率は二次救急で90%、三次救急でも80%と高い水準を維持しています。2024年は、二次救急当番日を昨年比で20日増やし133日対応しました。職員が使命感を持って取り組んでくれています。

受審に向けてどのような院内体制、準備体制を構築されましたか。
丸山課長:
病院機能評価受審にあたっては、院長以下27名から構成される「医療機能推進委員会」で進捗管理を行いました。院長を委員長として、院長補佐以上は全員、各部門の長が全員参加しています。本審査の14か月前(2023年5月)に日本医療機能評価機構の講演によるキックオフセミナーを開催。併せて、支援を受ける川原経営さんと委託契約を締結しました。
私自身が病院機能評価受審を進める経験が初めてだったこともあることから、スケジュールを立てるにあたり、前回(5年前)の受審スケジュールを確認し、一覧にしました。これで全体のスケジュール感が掴めました。
コンサルティングサービスを活用したメリットがあれば教えてください。
小嶋院長:
コンサルティング会社という外部の第三者に入っていただき、ご指摘をいただくことにより、職員の意識が高まる効果がありました。具体的な方策やノウハウを示していただきながら取り組むことで、効率よく進められました。
石倉副院長:
病院機能評価の重要な点は、多職種が一体となり目的に向かうことです。うまく方向づけをしてくれたのが川原経営さんでした。特に模擬審査がとても良かったです。前回受審時にもご支援いただいていたので、当院の特徴をよくご理解いただいている安心感がありました。当院の強みや以前より改善しているところを明確化し、褒めてくれたことがモチベーションになったようです。“元気が出た”、本番まで頑張ろうと師長が口々に言っていたのが印象的でした。
山本事務局長:
病院機能評価の審査に向けての準備、無事クリアするレベルに到達するまでにどの様に取り組んだら良いかを示していただきました。最初から最後まで寄り添っていただき、最終的には喜びを分かち合えました。

丸山課長:
病院機能評価の審査で求められる項目や水準は冊子を見れば分かりますが、実際の解釈は病院ごとに違います。川原経営さんからの対面でのご指摘や、各部署からの質問への回答などにより、解釈を現場に還元させることができました。
準備期間中に生じた課題と対応策を教えてください。
小嶋院長:
病院機能評価受審において難しいのは、職員全体の意識づけです。院内での取り組みはもちろんのこと、川原経営さんに外部の目線から助言を受けながら行ったケアプロセスなどにより、ますます細かく症例を検討するようになりました。今回指摘された同意書については、病院機能評価認定後も、更に、改善していこうということで取り組んでいます。徐々に意識が変わり、患者さんのために改善しようという流れになってきました。
石倉副院長:
意識づけという意味では、看護師長がカギだと思っています。そこから波及して一体感が生まれます。私が努めて気を付けたのは「こうしなさい」とは言わなかったことです。病院機能評価に向けてではなく、医療の質を上げるために、患者さんのためにはどうしたら良いかディスカッションを促しました。その結果、職員の達成感につながったと思います。
丸山課長:
病院機能評価の目的は落とすためではなく、医療の質を上げるためです。当院では、今回対象にはなりにくい診療科も含め、全ての診療科のケアプロセスを実施しました。これにより院内の共通項ができたように思います。ケアプロセスという場が領域、職種を超えた一体感につながりました。
山本事務局長:
当初は他人事のような職員もいたかもしれません。ケアプロセスを通じて、徐々に意識づけしながら“自分事”に波及させていくことが重要です。また、スケジュール管理も徹底しました。本審査が近づくにつれ機運を盛り上げいていき、徐々にまとまっていった感じがありました。
病院機能評価受審によって、どのような成果がありましたか。
石倉副院長:
私は当院での受審経験が今回で3回目です。この間、病院機能評価が求める“医療の質”の中身が変わってきていると肌で感じています。昨今、日常業務では多職種間のコラボレーションが重要になってきていますが、専門職は自身の業務を主にした発想になりがちです。受審を契機に、患者さんのための医療の質の向上が目標であることが明確になり、多職種との連携がスムーズになりました。さらに、院内に留まらず他の医療機関との連携にも広がりました。
山本事務局長:
私は初回の受審時に携わった経験があります。当時はまだ診療報酬上の評価も少なく、病院機能評価は時代とともに内容が変わっています。病院が成長するという意味でも、大きな取り組みであったと考えています。
丸山課長:
医療の質を担保するための活動には、裏付けとなる収益も必要です。病院機能評価(第三者評価)の認定を受けていることが診療報酬上の要件とされていたり、望ましいとされていたりする項目が増えてきています。要件となっている急性期充実体制加算1や緩和ケア病棟入院料、望ましいとされている感染対策向上加算1、救命救急入院料の充実段階評価などによる経営収入は、当院が地域で果たすべき役割のためには、欠かせないものです。
今後の展望をご教示ください。
小嶋院長:
主に病院機能評価受審についての委員会であった「医療機能推進委員会」ですが、認定を受けたから終了とするのではなく、これを継続的に行う予定です。定期的に委員会を開催し、今回受けた指摘の改善や医療の質の向上に向けた取り組みを行っていくことが重要だと考えています。
石倉副院長:
副看護部長からは、ケアプロセスにおいては、丁寧に症例を振り返ることで、とにかく考える機会になったと聞いています。経験を言語化したり、記録に残したりということの重要性を理解しました。大事にしていることの真髄ということも見えました。現場では病院機能評価の本審査が終わった後も、自主的に週に1回、各病棟の師長がケアプロセスを継続しています。

病院機能評価をこれから受審される医療機関の皆様へ一言お願いします。
小嶋院長:
繰り返しになりますが、外部の評価を受けることによって病院の改善すべき点が明確になります。病院の運営を改善する機会にしていただきたいと思います。
石倉副院長:
病院機能評価受審にあたっては、看護部が中心にならないといけないと思っています。24時間365日患者さんのそばにいますので、看護師から発信して皆に声をかけ、広がっていくと思っています。院内で何か問題が起こったときの解決には、部門間の連携が欠かせません。そのためには普段から会話、対話をする。普段できていないことは、いざ何かが起こったときにもできません。病院機能評価受審までのプロセスを、院内のコミュニケーションを起こす機会にしていただくと良いと思います。
山本事務局長:
ある意味求められる水準・機能を有しているかのテストを受ける様な事とも言えますので、外部評価で求められるレベルは、現代の病院運営において求められる標準であることを理解しながら、粛々と進めることが大事だと思います。
丸山課長:
現行の医療水準や法律と照らして、自院の運営が適正なのか、自分たちだけでは客観的に判断することは難しいです。外部から評価いただくことが、結果的には医療の質の向上、患者サービスの向上につながります。病院機能評価を受けることで、良いところは伸ばし、改善すべきところは改善するための機会になると思います。
貴重なお話をありがとうございました。
取材日 2025年1月20日

 お電話でのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ メールフォームからのお問合せ
メールフォームからのお問合せ